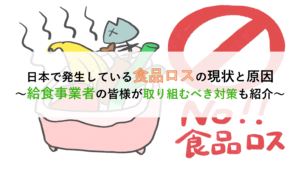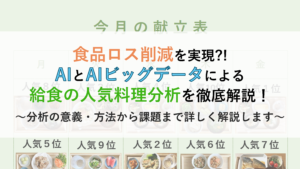食材費高騰の原因とは?給食事業者の皆様向けの対策も紹介!
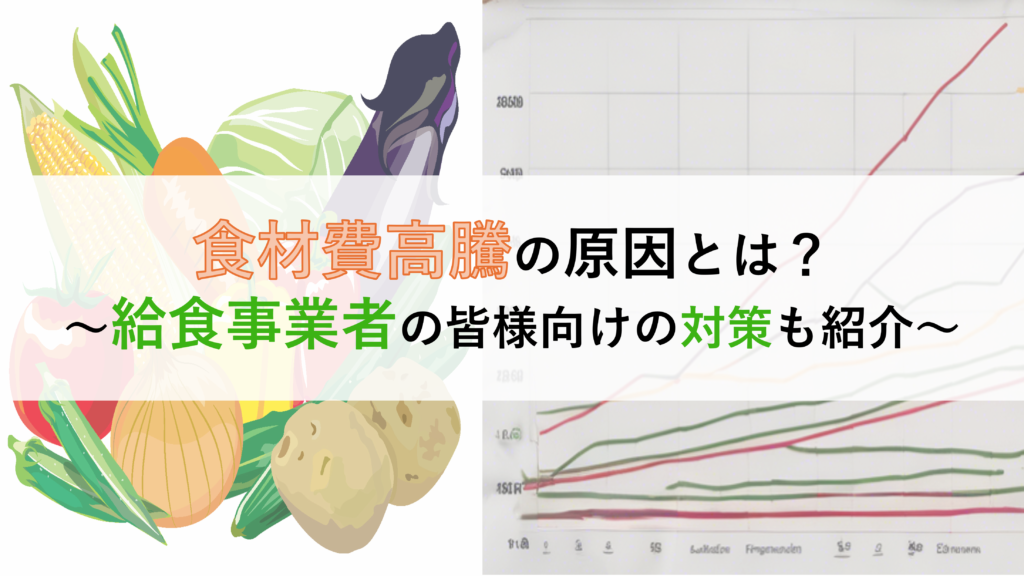
近年、食材の価格が高騰し、給食事業にも大きな影響を及ぼしています。食材費の高騰は、栄養バランスを保ちながら、限られた予算の中で献立を作成することを難しくしています。
本コラムでは、給食事業者が理解しておくべき食材費高騰の原因を詳しく説明し、具体的な対策も併せてご紹介します。
食材費高騰の原因
食材費高騰の原因として、以下の5つを詳しく説明します。
- 気候変動の影響
- エネルギーコストの上昇
- 国際貿易と供給チェーンの不安定
- 需給バランスの変化
- 円安と輸入依存
原因①:気候変動の影響
干ばつや洪水などの気候変動は、農作物の生育を阻害します。これにより、収穫量が減少し、食材価格が高騰します。
例えば、小麦や米といった主要穀物の生産が不安定になることで、価格が上昇しています。特に、小麦は世界三大穀物の一つであり、2021年にはカナダの干ばつによる収穫量減少が価格高騰の一因となりました。
原因②:エネルギーコストの上昇
石油やガスの価格高騰は、農業機械の運用コストや食材の輸送コストの増加に繋がり、食材価格の上昇に影響を与えています。特に、2022年にはロシア・ウクライナ紛争の影響でエネルギー価格が急騰し、世界的に食料価格の上昇を加速させました。
さらに、化学肥料や農薬の生産にもエネルギーが必要となるため、これらの価格上昇も食材価格全体に波及しています。
原因③:国際貿易と供給チェーンの不安定
政治的対立や貿易政策の変化が、食材の国際取引に影響を与え、食材供給チェーンの不安定化を招いています。特に、2022年のロシア・ウクライナ紛争は、小麦や肥料の主要な輸出国である両国の輸出を阻害しました。
例えば、家畜の飼料に使用される穀物の価格上昇は、肉類の価格にも波及しています。日本の場合、家畜の飼料は牧草などの「粗飼料」と、トウモロコシや大豆油かすを混ぜた「濃厚飼料」から成り立っています。そのため、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は、トウモロコシの主要輸出国であるウクライナの輸出量を減少させ、結果として肉類の価格が高騰しました。
原因④:需給バランスの変化
世界人口の増加と都市化は、食料需要を持続的に押し上げています。国連の「世界人口予測」では、2050年までに世界の人口が約97億人に達すると予測されており、この人口増加が食料需要を一層加速させる要因となっています。
特に、新興国の経済成長に伴い、肉類や乳製品に対する需要が急速に増加しています。経済協力開発機構(OECD)および国際連合食糧農業機関(FAO)によれば、世界全体の肉類消費は今後数十年にわたり増加し続けるとされています。具体的には、肉類の消費は2033年までに約15%増加し、特にアジア地域での需要が顕著に増加する見込みです。
こうした需要の高まりは、食材価格を上昇させ、市場全体に広範な影響を与えています。
原因⑤:円安と輸入依存
日本の輸入依存度は約6割強で海外からの食料供給に依存している状況です。特に大豆や小麦は約9割、果実は約6割、肉類は約5割を海外から輸入しています。このため、円安は輸入食材の価格上昇に直結し、日本の食材価格に影響を与えています。
給食事業者としての対策
食材価格の高騰は、給食事業者にとっても大きな課題となっています。限られた予算の中で、栄養バランスの取れた献立を作成することは容易ではありません。以下に、具体的な対策を示します。
対策①:代替食材の活用
高騰している食材の代わりに、同様の栄養価を持つ代替食材を取り入れましょう。例えば、小麦の価格が上昇している場合、米粉やコーンフラワーといった他の穀物を使用することで、コストを抑えつつ栄養を確保できます。
また、輸入食材の代わりに価格が安定している国産食材を取り入れることも効果的です。国産食材の活用により、食材費を抑えながら、地産地消を推進することもできます。
対策②:食材調達の工夫
地元の生産者と連携することで、食材費を抑えることができます。具体的な連携方法として、以下のようなアプローチが考えられます。
- 産地直送契約: 仲介業者を介さずに、地元農家や漁師から直接仕入れることで、安価に食材を調達できます。契約内容は、単価、納品時期、品質基準などを明確に定め、安定供給を確保しましょう。例えば、年間契約で一定量の野菜を確保することで、価格変動のリスクを軽減できます。
- 共同購入の実施: 地元の他の給食事業者と共同で食材を購入することで、まとめ買いによる価格交渉力が強化され、コスト削減が可能になります。
- 農業法人との連携: 農業法人は、生産者と消費者をつなぐ役割を果たします。地元の農業法人から食材を購入することで、地産地消を推進し、価格の安定を図ります。具体的には、生産計画の調整や価格の安定化を通じて、安定した供給を確保します。
このような連携により、地産地消が推進され、安定した食材供給が可能になります。給食事業者の規模やニーズに合わせて、最適な連携方法を選択することが重要です。
対策③:献立作成AIの活用
食材費が高騰する中で、限られた予算内で栄養バランスの取れた献立を作成することは、栄養士にとって大変な作業です。代替食材を用いた料理を考えるだけでなく、そのメニューを基に献立を組む際には、予算と栄養バランスの両方を考慮する必要があります。
しかし、献立作成AIを活用することで、この負担は大幅に軽減されます。AIは、料理データ、食材の価格、栄養価を学習し、献立を自動で作成します。このとき、AIは予算と栄養バランスの条件を満たした献立を作成します。そのため、代替食材を用いた料理データを新たに学習させれば、食材費高騰に対応しつつ、予算と栄養バランスの条件も満たした献立を作成できます。
つまり、献立作成AIを活用することで、栄養士は代替食材を用いたメニュー開発に専念できます。
Well-Fedの献立作成AIは、食材費高騰に対応しつつ、栄養バランスの取れた献立を自動で作成します!
まとめ
食材費の高騰は、気候変動や円安と輸入依存など、複数の要因によって引き起こされます。
給食事業者は、食材費高騰に直面し、献立の見直しを余儀なくされているでしょう。しかし、技術を活用した献立作成は、こうした課題に対する有効な対策となります。
Well-Fedの献立作成AIは、食材費の高騰に対応した献立を自動で作成します!
このAIは、学校給食から学食・社食など、様々なシーンでご活用いただけます。食材費高騰に対応した献立作成でお困りの方は、ぜひ一度Well-Fedにご相談ください。
お問い合わせ先:info@well-fed.jp